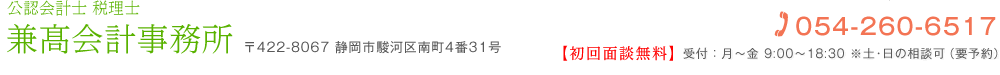【国税庁】令和2年度における再調査の請求の概要
【国税庁】令和2年度における審査請求の概要
【国税庁】令和2年度における訴訟の概要
国税庁から、令和2年(2020年)度における、再調査の請求、審査請求、訴訟の概要が公表されました。
「再調査の請求」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、
その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。
「審査請求」は、税務署長や国税局長などが行った処分に不服がある場合に、
その処分の取消しや変更を求めて、国税不服審判所長などに対して不服を申し立てる制度です。
納税者は、「審査請求」という行政上の不服申立てを経た後、なお不服があるときは、
裁判所に対して「訴訟」を提起することができます。
再調査の件数は、前年より13.0%減少し、認容されたのは10.0%(前年12.4%)となりました。
審査請求の件数は、前年より18.7%増加し、認容されたのは10.0%(前年13.2%)となりました。
訴訟の件数は、前年より26.0%減少し、納税者勝訴は14件(7.8%)となりました。
「再調査の請求」、「審査請求」、「訴訟」を行う際の手続きは、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓
【国税庁】税務署の処分に不服があるとき