【名古屋国税局】平成28年分 年末調整等説明会の御案内(源泉徴収義務者の皆様へ)
【名古屋国税局】平成28年分 青色申告決算等説明会のご案内(青色申告者の皆様へ)
10月も半ばになり、年末調整や、個人事業者の決算の時期が近づいてきました。
今年も、各税務署では、年末調整等説明会や、青色申告決算等説明会が、開催されます。
上記リンク先は、名古屋国税局管内ですが、他の地区でも同様に開催されます。
特に、今年会社を設立した方、今年初めて従業員を雇用された方は、参加されると良いでしょう。

【名古屋国税局】平成28年分 年末調整等説明会の御案内(源泉徴収義務者の皆様へ)
【名古屋国税局】平成28年分 青色申告決算等説明会のご案内(青色申告者の皆様へ)
10月も半ばになり、年末調整や、個人事業者の決算の時期が近づいてきました。
今年も、各税務署では、年末調整等説明会や、青色申告決算等説明会が、開催されます。
上記リンク先は、名古屋国税局管内ですが、他の地区でも同様に開催されます。
特に、今年会社を設立した方、今年初めて従業員を雇用された方は、参加されると良いでしょう。
クラウドの活用が広がってきていますが、
脱税の調査においても、国税犯則取締法を改正し、
など、権限が強化されます。
来年度税制改正大綱に盛り込まれる方針です。
【国税庁】源泉所得税関係・・・各種様式
【国税庁】「平成28年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)」
10月に入り、今年も残すところ3ヶ月となりましたが、
国税庁から、「平成28年分 年末調整のしかた」など、年末調整関係の資料が公表されました。
今年度の主な留意事項は、以下の通りです。
その他詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
また、各税務署では、11月頃、説明会を開催すると思います。
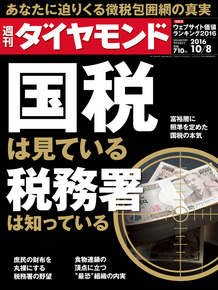
現在書店等で発売中の週刊ダイヤモンド2016年10月8日号は、「国税は見ている 税務署は知っている」という特集が組まれています。
という、少し気になるサブタイトルがついています。
内容については、
などについて、詳細に書かれています。
富裕層の方、サラリーマンの方、個人で事業を営んでいる方、専業主婦の方も、
是非一度目を通すとよいと思います。
【産経】配偶者控除103万円超も 政府、年収要件緩和案が浮上
数年かけて行う予定の所得税改革の1つに、配偶者控除から夫婦控除への移行が、挙げられていました。
所得税改革の詳細は、こちらをご覧下さい。 ↓
【日経】所得税、数年かけ改革 基礎控除も見直し【2016年9月20日付ブログ】
しかし、早くも、夫婦控除の導入は先送りにし、配偶者控除の年収要件(103万円以下)を緩和する(引き上げる)方向で検討されているようです。
夫婦控除の導入は、増税となる世帯が出てくるため、反発が予想されることから、時間をかけた議論を行う方向になったようです。
年末の大綱公表まで、まだ動きがありそうですね。
最近、「配偶者控除廃止」、「夫婦控除導入」という言葉をよく目にすると思います。
所得税改革に関しては、これだけにとどまらず、数年かけて、抜本的に見直すようです。
全体像は、以下の通りです。
第1弾 女性の社会進出、若年層の子育て支援
第2弾 控除制度を多様な働き方に対応
第3弾 老後の資産形成を支援
第1弾では、夫婦控除の導入の他、基礎控除(現行一律38万円)を、年収別に差を設けたり、
扶養控除や社会保険料控除の見直しも検討されます。
第2弾では、基礎控除を拡大する一方で、サラリーマンが経費部分として控除できる給与所得控除の縮小などが検討されます。
政府は、改正前後で、所得税収がほぼ同じであることを基本に据えていますが、
個々に見ると、得する人、損する人がいると思われ、最終決着までには紆余曲折が予想されます。
今後の議論の行方には注目ですね。
【時事通信】「夫婦控除」来年にも=時間外見直し、罰則必要-茂木自民政調会長
ここ数日、所得税改革の一環として、配偶者控除の廃止、夫婦控除導入、という話題が挙がっていますが、
実現可能性が高そうですね。
ポイントは、現制度と比較して増税となる世帯への配慮と、所得制限をどこで設けるか、でしょうか。
また、長時間労働是正については、罰則の導入など厳格化を図るようです。
働き方が変わってきます。
雇用する経営側も、しっかり対応していくことで、いい人材の確保をしていきたいですね。
【産経】政府税調、配偶者控除の見直しに着手 「夫婦控除」への転換軸、11月めどに見解
9日に政府税制調査会の総会が開催されました。
これまでの報道にありますように、配偶者控除の見直しを中心とした、所得税改革について、議論されたようです。
専業主婦世帯を優遇する「配偶者控除」から、共働き世帯も負担軽減になる「夫婦控除」を創設する案が出ています。
「夫婦控除」を創設するに当たり、財源の問題から所得制限を設けるようですし、
制度改正により増税となる世帯からの反発も予想され、どのような形で決着するかはまだ見えません。
11月をめどに見解をまとめるようです。これから1ヶ月半程度の議論の行方に注目ですね。
政府税制調査会では、本日(9月9日)に会合を開き、
来年度(2017年度)税制改正に関する議論をスタートします。
先日、各省庁からの要望が出揃いました。(詳細はこちら ↓)
平成29年度税制改正要望、出揃う【2016年9月2日付ブログ】
それらを含め、近年話題となっている、配偶者控除見直しなどの所得税改革や、
海外子会社を利用した課税逃れ防止策強化などについて、議論されるようです。
年末の大綱公表まで、どのような議論がされるか注目です。
電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました(平成28年8月)
電子帳簿保存法の改正により、
領収書をスマートフォンによる保存が可能になりました。
ただし、このためには、「3ヶ月前の日」までに、申請書を提出しなければなりません。
仮に来年1月1日から適用を受ける場合は、今年9月30日に申請書を提出しなければなりません。
申請書の受付自体が、9月30日から開始のため、「9月30日」だけに限られます。
来年1月1日から適用を受ける方は、ご注意下さい。