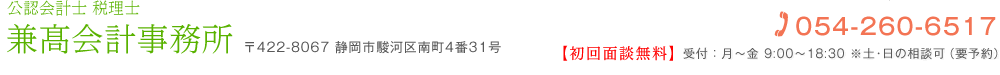昨年議論の俎上に上りましたが、立ち消えとなってしまった「配偶者控除見直し」。
自民党の「女性活躍に資する制度検討ワーキンググループ(WG)」が開催され、議論されたようです。
税制だけ変えても効果はどれだけ上がるのか、という意見もありますが、
先日は、トヨタ自動車が、配偶者手当を廃止し、子供手当を4倍増にすることを、労組と協議している、というニュースが流れました。
税制の方は、年末の税制改正大綱公表へ向けて、議論が進められていきますので、今後の動向に注目です。
企業の改革は、特に中小企業では、すぐにでも出来ます。
経営者は、よいと思ったことを、ためらわずに、トライしてみましょう。