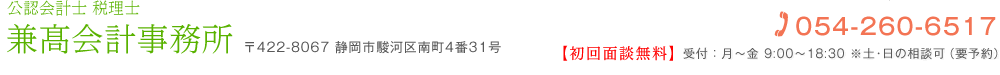国税庁のHPに、「相続税・贈与税・事業承継税制関連情報」が掲載されました。
ここでは、平成25年度税制改正により、平成27年1月1日から適用となる、相続税・贈与税関連の情報が、まとまっています。
主な改正点は、以下の通りです。
1 相続税
(1) 遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。
(2) 最高税率の引上げなど税率構造が変わります。
(3) 税額控除のうち、未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます。
(4) 小規模宅地等の特例について、特例の適用対象となる宅地等の面積等が変わります。
2 贈与税
(1) 相続時精算課税について、適用対象者の範囲の拡大など適用要件が変わります。
(2) 暦年課税について、最高税率の引上げや税率の緩和など税率構造が変わります。
3 事業承継税制(相続税・贈与税)
事業承継税制について、適用要件の緩和や手続の簡素化など制度の適用要件等が変わります。
こちらも合わせてご覧下さい。
↓↓↓
相続税増税(基礎控除の引き下げ)の適用は来年(2015年)1月からです【2014年1月6日ブログ】
【間違いやすい税務実務】相続時精算課税を適用する際の年齢はいつ時点?【2014年1月22日ブログ】