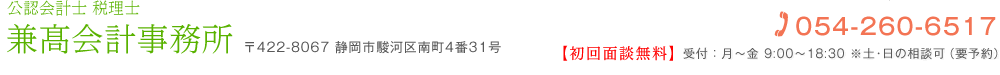3月27日に、令和2年度税制改正法案が国会で成立しました。
財務省から、「令和2年税制改正」パンフレットが公表されました。
今回の主な改正項目は、
1.個人所得課税・資産課税
- 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
- NISA(少額投資非課税)制度の見直し・延長
- エンジェル税制の見直し
2.法人税制
- オープンイノベーションの促進に係る税制の創設
- 投資や賃上げを促す措置
- 連結納税制度の見直し
3.消費課税
- たばこ税の見直し
- 法人に係る消費税の申告期限を延長する特例の創設
- 居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化
などです。
パンフレットは、図解入りで分かりやすく書かれていますので、是非ご一読下さい。