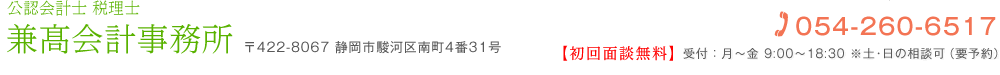京都市では、10月1日から、宿泊税が導入されました。
東京都、大阪府に次ぐ3例目です。
東京都、大阪府と異なる点は、民泊を含む全宿泊者を対象としている点で、
上限が1,000円(宿泊料金5万円以上)(東京都の上限は200円、大阪府は300円)です。
税収見込みは、平年度45.6億円で、東京都(25億円)及び大阪府(7.8億円)と比較しても、かなり大きいです。
他の自治体では、金沢市が2019年4月から導入され、その他も検討中の自治体もあります。
なお、東京都に関しては、東京五輪中は、宿泊税の課税停止を決めました。
詳細はこちら ↓
【東京都】東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴う宿泊税の課税停止について(お知らせ)