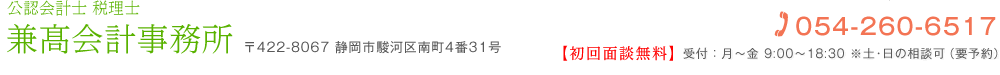【財務省】「令和6年度税制改正(案)のポイント」(令和6年2月)
財務省から、「令和6年度税制改正(案)のポイント」(令和6年2月)が公表されました。
図解入りで分かりやすく解説されています。
改正内容は以下の通りです。
個人所得課税
- 所得税・個人住民税の定額減税
- ストックオプション税制の利便性向上
- 住宅ローン控除の拡充
資産課税
- 法人版事業承継税制の特例措置に係る特例承継計画の提出期限の延長
法人課税
- 賃上げ促進税制の強化
- 戦略分野国内生産促進税制の創設
- イノベーションボックス税制の創設
- 中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充
- 第三者保有の暗号資産の期末時価評価課税の見直し
- 交際費から除外される飲食費に係る見直し
消費課税
- プラットフォーム課税の導入
国際課税
- 非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交換のための報告制度の整備等
納税環境整備
- GビズIDとの連携によるe-Taxの利便性の向上
- 更正の請求に係る隠蔽・仮装行為に対する重加算税制度の整備