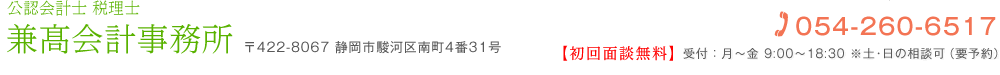【国税庁】平成29年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
【時事通信】1億円超収入、300人規模=仮想通貨売買活発で-国税庁
国税庁から、「平成29年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」が、公表されました。
3月15日に提出期限を迎えた確定申告のまとめです。
所得税では、事業所得者の納税人員、所得金額、申告納税額が、前年と比較して減少する一方、
事業所得者以外はいずれも増加しています。
また、雑所得が1億円超あった納税者のうち、仮想通貨の売買で収入を得ていた人が331人いるそうです。
譲渡所得は、土地、株式とも、申告人員、有所得人員及び所得金額が前年と比較して増加しています。
消費税は、主に事業所得者が対象となるためか、申告件数及び申告納税額は前年と比較して減少しています。
贈与税は、申告人員、納税人員、申告納税額とも、前年と比較して減少しています。
その他詳細は、リンク先をご覧下さい。