国税庁から、「平成25年分贈与税の申告のしかた」及び「様式一覧」が公表されました。
平成25年分の贈与税の申告は、平成26年3月17日までに行う必要があります。
平成25年中に、110万円以上の贈与を受けた場合は、忘れずに申告しましょう。
当事務所では、贈与税申告のお手伝いもしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
054-260-6517

国税庁から、「平成25年分贈与税の申告のしかた」及び「様式一覧」が公表されました。
平成25年分の贈与税の申告は、平成26年3月17日までに行う必要があります。
平成25年中に、110万円以上の贈与を受けた場合は、忘れずに申告しましょう。
当事務所では、贈与税申告のお手伝いもしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
054-260-6517
12月12日に、平成26年度与党税制改正大綱が公表されました。
ポイントは、ほぼこれまで報道されていた通りです。
・復興法人税は1年前倒しで廃止
・軽減税率は、消費税10%時に導入と明記されましたが、具体的導入時期は記載なし
・自動車取得税は引き下げるが、軽自動車税は新車について引き上げる
・交際費は飲食に関する支出のうち50%を非課税(損金算入)
上記以外については、リンク先をご覧下さい。
【国税庁】平成24事務年度における相続税の調査の状況について
国税庁は、11月20日に、「平成24事務年度における相続税の調査の状況について」を公表しました。
調査件数12,210件に対し、申告漏れ等の非違があった件数は9,959件もあり、何と全体の81.6%に上ります。
金額でみると、申告漏れ課税価格は3,347億円で、実地調査1件当たりでは2,741万円です。
申告漏れ相続財産の金額の内訳は
現金・預貯金等1,236億円
土地560億円
有価証券431億円
となっています。
現金・預貯金等については、意図的に隠したケースもあるかもしれませんが、
名義預金(名義は相続人など他の人になっているが、実質は被相続人の預金であるもの)が、
相続財産から漏れているケースがかなり多いと考えられます。
相続財産の申告漏れとならないように、注意したいですね。
名義預金の詳細についてはまた後日。
今年から、「国外財産調書の提出制度」が始まりました。
これは、12月31日時点で、国外に5,000万円以上の財産を有する方は、翌年3月15日までに「国外財産調書」を提出する、というものです。
なお、2014年の場合は、3月15日が土曜日のため、17日(月)が提出期限となっています。
不提出の場合には罰則があり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
この度、国税庁から、FAQが公表されました。該当する方は、ご一読下さい。
制度の概要については、こちらもご覧下さい。
↓↓↓
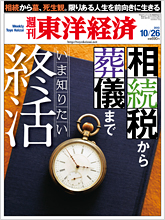
来年4月の消費税率8%アップにかき消されそうですが、相続・贈与税の改正も忘れてはいけません。
10月26日号の週刊東洋経済では、相続の特集が組まれています。
相続税、葬儀・墓、遺言書などが取り上げられています。
その中でも、相続税に関しては、改正前後の相続税額のシミュレーションや、改正についての解説、注意事項などが、書かれているので、必見です。
実際に相続税額のシミュレーションをするに当たっては、留意点が何点もあるので、専門家に相談されるのがよいでしょう。
注目されていた、非嫡出子の相続差別について、9月4日最高裁大法廷で、違憲との判断が下されました。
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことで、
民法では、法定相続分が、嫡出子の2分の1と規定されています。
今回の違憲判断は、過去に確定した法律関係には、影響を及ぼさないとされています。
逆に、未確定であれば、効力があります。
なお、政府は民法改正を急ぐ考えのようで、早ければ秋の臨時国会で改正されます。
非上場株式の評価方法の1つに、類似業種比準方式という方法があります。
これは、事業内容が類似する上場企業の株価をもとに、自社の配当金額、利益金額、純資産価額の3つの要素を比較することで、株価を算定する方法です。
その計算の際に使用する上場企業の株価は、毎月国税庁から公表されています。
8月1日公表分はこちら
↓↓↓
「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
これによりますと、ほとんどの業種の株価が、平成24年11月から平成25年5月にかけて上昇しています。
類似業種の株価上昇により、予想外に自社の株価が上昇している会社もあるかと思います。
そのため、相続税負担額が増えることが予想されます。
自社株の評価算定をしたことがない会社は、一度算定してみるとよいでしょう。
また、算定したことがある会社でも、この機会にもう一度、算定してみるとよいでしょう。
その上で、必要があれば、専門家に、自社株の評価を下げるなどの相続対策を相談し、検討しましょう。
会社法では、種類株式は9種類定められています。
1.剰余金の配当
2.残余財産の分配
3.議決権制限
4.譲渡制限
5.取得請求権
6.取得条項
7.全部取得条項
8.拒否権
9.役員選任権
発行するには、定款で定める必要があります。
定款の変更には、株主総会の特別決議(※)が必要です。
(※)議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成による決議
種類株式を組み合わせて使えば、経営の幅が広がり、事業承継にも有効な手段となります。
一方で使い方を誤ると、問題が起きる場合がありますので、注意が必要です。
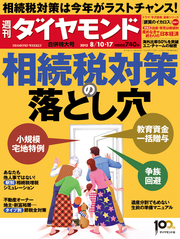
2015年1月から、相続税の基礎控除が縮小され、最高税率が引き上げとなり、相続税対策が気になる方も多いかと思います。
今週号の週刊ダイヤモンドでは、相続税対策を特集されています。
節税には、いろいろな方法があり、うまく使えば得になりますが、使い方を誤ると大変です。
また、節税だけを考えて対策を取ると、後で残された人が困ったり、もめごとを引き起こしたりすることもあります。
最適な方法は、置かれた状況によって、異なります。
相続対策は時間がかかりますので、早めに対応しておきたいですね。