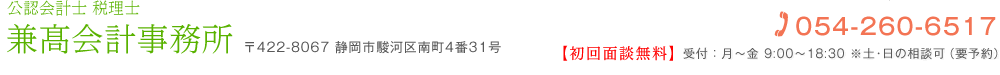1月20日施行の「産業競争力強化法」により、企業の提案に基づき「規制改革」を実行する新たな制度が創設されました。
「企業実証特例制度」
・・・新規事業にチャレンジする事業者が、規制の特例措置を提案。安全性等の確保を条件として「企業単位」で規制の特例措置の適用を認めるもの
① 事業者が、規制の特例措置を提案。
② 事業・規制所管両大臣が協議し、特例措置を創設。
③ 安全性等を確保する措置を含む事業計画の認定を通じ、 規制の特例措置の利用を認める。
「グレーゾーン解消制度」
・・・事業者の新規事業の計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を照会。躊躇なく事業を実施
できるよう後押し
① 事業者が、事業計画に即して、規制の適用の有無を照会。
② 事業所管大臣を通じ、規制所管大臣に確認を求める。
③ 規制所管大臣から回答を得る。
1月に、以下の特例措置が認められています。
「企業実証特例制度」
①半導体製造に用いるガス容器の先進的検査手法の導入
②新しいタイプの水素タンクの導入による燃料電池フォークリフトの実用化
③物流に用いるアシスト力の大きいリヤカー付電動アシスト自転車の公道走行
「グレーゾーン解消制度」
①運動機能の維持など生活習慣病の予防のための運動指導
②血液の簡易検査とその結果に基づく健康関連情報の提供
③緊急時における自動走行機能を備えた自動車の公道走行
新規事業を検討されている企業は、この制度への申請も検討されては、如何でしょうか。