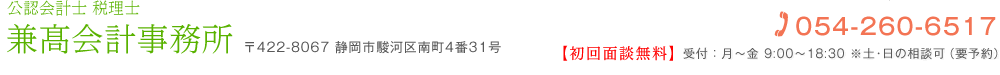カテゴリー別アーカイブ: ブログ
均等割は引き上げ?
外形標準課税、均等割、ともに赤字企業でも納税義務が発生します。
法人税減税の代替財源として、議論の俎上に上ってきましたが、
外形標準課税は、2015年度は中小企業まで対象を広げない方針のようですが、
均等割は、2015年度から引き上げる方針のようです。
これから年末に予想される来年度の税制改正大綱が公表されるまで、様々な議論が繰り広げられると思います。
議論の行方に注目です。
ロータリークラブの会費は経費にならない?
ロータリークラブの会費等は必要経費に算入できないとした事例(平成22年分及び平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年3月6日裁決)
平成26年1月~3月分の国税不服審判所による裁決事例が公表されました。
この中で、注目される裁決を取り上げます。
ロータリークラブの会費等が、必要経費か否かについて、争われました。
この件については、過去にも必要経費に算入できない、という裁決事例がありますが、
今回もまた同じような結果が出ました。
請求人(納税者)は、営業活動の一環として、ロータリークラブに入会し、本件クラブの活動に継続的に参加することにより、
顧客を獲得しているので、会費等は必要経費、と主張しています。
しかし、審判所は、ロータリークラブの活動が、請求人の業務と直接関係するとはいえず、
業務遂行上必要なものとはいえないので、必要経費とは認められない、との判断をしています。
ロータリークラブやライオンズクラブなどに加入されている方は、会費等の処理に当たり、
これらの裁決事例を参考にして下さい。
年末調整等説明会開催
平成26年分 年末調整等説明会の御案内(源泉徴収義務者の皆様へ)
各地で、11月くらいに、年末調整等説明会が開催されます。
上記リンク先は、名古屋国税局管内ですが、他の地区でも同様に開催されます。
特に、今年会社を設立した方、今年初めて従業員を雇用された方は、出席をご検討下さい。
国税不服審判所・・・裁決事例は税務実務の参考に!
国税不服審判所から、平成26年1月~3月の裁決事例が、公表されました。
国税不服審判所は、国税局や税務署とは別の機関です。
納税者が、課税処分等に不服がある場合に、異議申し立てを行った後に、処分の取消しや変更を求めて審査請求すると、
国税不服審判所長は、原処分が適正で あったかどうか判断するため調査・審理を行い、その結果(裁決)を 下します。
裁決に不服がある場合は、裁判所に訴えを提起することができます。
国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。
↓ ↓ ↓
最近は、3ヶ月分ずつ事例が公表されます。
今回は、平成26年1月~3月分が公表されました。(なお、全てが公表されるわけではありません。)
事例は、税務実務の参考になりますので、気になる事例には目を通しておくとよいと思います。
【国税庁】「印紙税の手引き(平成26年9月)」公表
国税庁から、「印紙税の手引き(平成26年9月)」が公表されました。
印紙税に関わる方々は、ご一読下さい。
印紙税に関しては、平成26年4月から、領収証等にかかる非課税範囲が、3万円から5万円に拡大されています。
詳細はこちらをご覧下さい。
↓ ↓ ↓
印紙税法の改正・・・非課税範囲の拡大(2014年4月1日~)【2014年4月2日付ブログ】
印紙税は、「文書」にかかる税金です。
従って、「文書」に何が書かれているかが重要であり、その内容によって、税額が変わる可能性があります。
課税文書にも関わらず、うっかり課税文書と認識せずに印紙を貼付し忘れたために、調査で指摘されることがあります。
その場合は、過怠税が課されます。(詳細は手引きP15に記載されています)
例えば、「変更契約書」で、当初契約との変更内容が、支払条件など”金額”でない場合は、要注意です。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
印紙税は、税務代理の対象外ですが、当事務所のお客様に対しては、
印紙税の基本的考え方、文書の記載方法など、詳細に渡り、アドバイス致します。
マイナンバー制度
「マイナンバー制度」は、ご存知でしょうか?
「国民総背番号制度」とも言われることがあります。
国民1人につき1つの番号(12ケタ)が付与され、その番号で、年金・保険・税・災害対策などが管理される制度です。
法人にも番号が付与されます。
2015年10月から、マイナンバーの付番・通知が始まり、
2016年1月から、利用が開始されます。
トップのリンク先は特集ページですが、
以下のリンク先は、そのページの中にある解説ページです。
皆さん全員が関係することですので、是非ご一読下さい。
法定調書の提出枚数が1,000枚以上の場合は、e-Taxもしくは光ディスクでの提出義務があります
【国税庁】「光ディスク等による支払調書の提出が義務化されています」(平成26年9月)
【国税庁タックスアンサー】No.7455 法定調書の提出枚数が1,000枚以上の場合の光ディスク等による提出義務
【国税庁質疑応答事例】e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務
今年から、前々年(今年の場合は平成24年)の支払調書(種類ごと)が、1,000枚以上であった場合は、
e-Taxまたは光ディスク等による提出が義務付けられます。
該当する会社のご担当の方は、ご注意下さい。
こちらも合わせてご覧下さい。
↓ ↓ ↓
【日本公認会計士協会】「『経営者保証に関するガイドライン』における法人と経営者との関係の明確な区分等に関する手続等について」の公表
中小企業支援対応プロジェクトチームによる報告「『経営者保証に関するガイドライン』における法人と経営者との関係の明確な区分等に関する手続等について」の公表について
「経営者保証に関するガイドライン」及び「『経営者保証に関するガイドライン』Q&A」が、2014年2月1日から適用となっています。
詳細はこちらをご覧下さい。
↓ ↓ ↓
個人保証のあり方見直し(「経営者保証に関するガイドライン」策定)【2013年12月6日ブログ】
【金融庁】「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集の公表【2014年6月6日付ブログ】
この中で、経営者保証を提供することなしに資金調達することを希望する場合に、
以下のような経営状況であることが求められます。
① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離
② 財務基盤の強化
③ 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保
このうち、①に関しては、公認会計士等の外部専門家による検証を実施し、
その結果を、金融機関等に適切に開示することが望ましいとされています。
この際の、公認会計士による検証手続や報告書雛型等が、公表されました。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
兼髙会計事務所では、上記の法人と経営者との関係の明確な区分等に関する手続を行い、実施報告書を発行しております。
お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。
【時事通信】創業10年未満の政府調達促進
【時事通信】創業10年未満の政府調達促進=中小企業需要法案の概要判明
経済産業省が臨時国会に「中小企業需要創生法案」を提出するようです。
この中で、創業10年未満の中小企業の売上拡大を支援するために、
中央省庁ごとに、これらの企業からの調達を増やすための施策や目標を盛り込んだ契約方針を、
定めるそうです。
政府の創業支援への取り組みが、次々と打ち出されています。
創業を考えている方は、この流れに乗りたいですね。
<2014年10月3日追記>
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
兼高会計事務所では、創業を目指す皆様のサポートを承っております。
また、シークエンス ビジネスパートナー株式会社にて、経営者の育成業務を承っております。
お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。