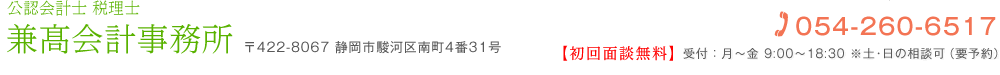【国税庁】「平成30年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
国税庁から、「『平成30年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」
が、公表になりました。
内容は、4月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。
4月までに相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。
多くの業種で、今年(平成30年)に入ってからの株価は高く、また、平成29年平均より、
各月の2年平均株価の方が安い傾向にあります。