「新規融資や経営改善・事業再生支援等における参考事例集」の公表について
金融庁は、「新規融資や経営改善・事業再生支援等における参考事例集」の公表しました。
一読されるとよいでしょう。
この事例集では、以下の分類ごと、合計55件の事例を取り上げています。
内訳は以下の通りです。
新規融資 14件
本業の収益改善(トップライン支援) 10件
経営改善・事業再生支援等 20件
創業支援 11件

「新規融資や経営改善・事業再生支援等における参考事例集」の公表について
金融庁は、「新規融資や経営改善・事業再生支援等における参考事例集」の公表しました。
一読されるとよいでしょう。
この事例集では、以下の分類ごと、合計55件の事例を取り上げています。
内訳は以下の通りです。
新規融資 14件
本業の収益改善(トップライン支援) 10件
経営改善・事業再生支援等 20件
創業支援 11件
雑誌の消費税率、来年4月以降は店頭で税率8%適用 来年3月以前の発売分でも
当初、経過措置では、2014年3月以前に発売された雑誌等を、4月以降に購入した場合、消費税率は5%になる、と規定されていました。
しかし、それでは店頭が混乱する、ということで、出版業界からの要望を受け、この経過措置を廃止することにしたようです。
従って、同じ雑誌でも、2014年3月中に購入すれば、消費税率は5%、4月1日以降(2015年9月まで)に購入すれば8%ということになります。
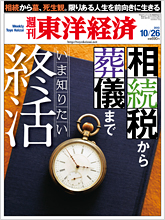
来年4月の消費税率8%アップにかき消されそうですが、相続・贈与税の改正も忘れてはいけません。
10月26日号の週刊東洋経済では、相続の特集が組まれています。
相続税、葬儀・墓、遺言書などが取り上げられています。
その中でも、相続税に関しては、改正前後の相続税額のシミュレーションや、改正についての解説、注意事項などが、書かれているので、必見です。
実際に相続税額のシミュレーションをするに当たっては、留意点が何点もあるので、専門家に相談されるのがよいでしょう。
損害賠償金は、通常、資産の譲渡等の対価に当たらないため、消費税は不課税取引に該当します。
しかし、「損害賠償」という名称によって判断するのではなく、実質で判断する必要があります。
例えば、損害を受けた製品をそのまま使用できる、あるいは軽微な修理により使用できる場合は、その損害賠償金の収受は、課税取引になりますので、注意が必要です。
【日商】小冊子「消費税率引上げ対策早わかりハンドブック」を無料配布します
日本商工会議所では、小冊子「消費税率引上げ対策早わかりハンドブック」を作成し、各地の商工会議所で無料配布しています。またリンク先からダウンロードできます。
図解入りで分かりやすく書かれいて、参考になります。是非ご一読下さい。
また、具体的な対策は、専門家と相談しながら進めるのがよいと思います。
2014年4月1日になって、慌てることのないよう、今から準備を進めるのがよいでしょう。
<主な内容>
ポイント1 消費税引き上げを乗り切る収益確保策を考えよう!
ポイント2 納税資金と資金繰りに注意しましょう!
ポイント3 消費税率引き上げに備えて社内体制を整備しましょう!
ポイント4 税率引き上げ後は新旧税率が混在。経理処理に注意しましょう!
ポイント5 中小企業の価格転嫁をサポート!新しいポイントの法律を押さえましょう!
業界団体の「全国清涼飲料工業会(全清飲)」では、転嫁カルテルを結ぶようです。
具体的には、以下の点で
(1)卸業者や流通大手などへ販売する際、本体価格に3%分を必ず転嫁する
(2)自動販売機では一部商品を10円単位で値上げし、価格を据え置く商品とあわせて全体として3%値上げする
なお、転嫁カルテルは、公正取引委員会に届け出る必要があります。
すでに法律が10月1日から施行されています。
注意点としては、”転嫁”カルテルであるため、消費税増税分の価格転嫁についてカルテルを結ぶことはOKですが、本体価格の値上げ等のカルテルを結ぶと、独占禁止法違反になります。
詳細はこちらをご覧下さい
↓↓↓
中小企業者(※)は、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得した場合、一括損金処理が可能です。
詳細はこちら
↓↓↓
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例【国税庁タックスアンサー】
(※)中小企業者とは、
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 (ただし、大規模法人に支配されている法人を除きます)
(2) 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
さて、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分を資本的支出といいます。
中小企業者が、30万円未満の資本的支出を行った場合、規模の拡張である場合や単独資産としての機能の付加である場合など、実質的に新たな資産を取得したと認められる場合には、中小企業者の特例が適用でき、一括損金処理できますが、そうでない場合には、適用できませんので、注意が必要です。
詳細はこちら
↓↓↓
金融庁、機関投資家に出資先への経営関与求める 年内に指針まとめ
「スチュワードシップ・コード」を呼ばれる機関投資家に出資先企業の経営陣らと経営戦略について意見交換したり、株主総会で議決権を行使したりして積極的に経営に関与するよう求める行動指針を、年内にまとめるようです。
金融庁では、すでに2回有識者検討会を開催しています。
日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会 (第1回)議事次第
日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会 (第2回)議事次第
第3回目は、10月18日開催予定です。
「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」(第3回)の開催について
義務的になるとうまくいかない可能性がありますが、他社のいいところを取り入れることで、企業価値の向上が図れるようになれば、よいですね。
財務諸表提出、2年分に限定=新規上場時の負担軽減-金融庁方針
現在、新規上場する際に、5年分の財務諸表の提出を求められます。
公認会計士による監査証明が付くのは、直近2期分ですが、それ以前3期分の提出も求められています。
当然、決算書は、毎期株主総会にて、承認(報告)を受けていますから、会社法に従ったものは作成していますが、提出に際し、その決算書を財務諸表等規則に従って組み替える必要があります。
また、公認会計士は監査対象外ですがチェックしますし、証券会社や取引所による審査対象になります。
そのため、事務負担がかなり重かったと思います。
今後、2年分のみに限定する方針のようです。
負担が軽減されるとよいのですが・・・。