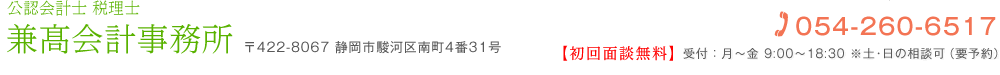経済波及効果、試算3兆円 コンパクト五輪実現
2020年のオリンピックの開催地が東京に決定しました。
経済効果は約3兆円と言われているそうです。
私は、楽しみにしているいくつかの競技があります。
中でも、≪7人制ラグビー(セブンズ)≫(以下、”セブンズ”)
??? と思われた方もいらっしゃるかと思います。
セブンズは、2016年リオデジャネイロ五輪からの、正式競技となります。
では、”セブンズ”とはどんな競技なのか。
セブンズは通常の15人制と競技場の広さが同じです。
人数が少ないこともあり、15人制のように大勢でもみ合ってボールを取り合うシーンは少なく、常にボールが動き、選手が走り回ります。
試合時間は、15人制では40分ハーフですが、7人制では7分ハーフです。
このように、15人制と7人制は、同じラグビーでありながら、しかも同じ競技場を使っているのに、全く別のスポーツですね。
ちなみに、東京オリンピックの前年2019年には、日本で15人制ラグビーのワールドカップが開催されます。
こちらも注目です。
ラグビーと7人制ラグビーの違いのように、経営においても、同じ商品・サービスでも少し視点(用途・売り先など)を変えることで、大ヒットした事例があります。
例えば、ポストイット(付箋)は、接着剤の失敗から生まれた商品です。
また、「シュレッダーはさみ」は、当初は刻み海苔用のはさみとして作られていたのが、生まれ変わったものです。
ちょっとした視点を変えるだけで、失敗からもヒット商品になることがある。ヒントはすぐそこに隠れているかもしれません。