市区町村別に、所得増減マップが公開されています。
1976年から2016年までデータがあります。時代ごとの景気の動向が見て取れます。
増加は暖色系、減少は寒色系で表示され、金額が多いほど色が濃く表示されています。
2016年は日本全体が明るい感じ(所得が増加)していますが、ところどころに寒色系が点在しています。
皆さんは如何でしょうか?

市区町村別に、所得増減マップが公開されています。
1976年から2016年までデータがあります。時代ごとの景気の動向が見て取れます。
増加は暖色系、減少は寒色系で表示され、金額が多いほど色が濃く表示されています。
2016年は日本全体が明るい感じ(所得が増加)していますが、ところどころに寒色系が点在しています。
皆さんは如何でしょうか?
【名古屋国税局】資産税(贈与税及び譲渡所得)関係 特例適用チェック表
名古屋国税局から、「資産税(贈与税及び譲渡所得)関係 特例適用チェック表」が、公表されました。
以下の特例を適用する場合には、チェックシートを使い、要件を満たしているか、
申告書に添付する書類、について、確認してみるとよろしいかと思います。
各省庁から、平成31年度税制改正要望が、財務省HPにまとめられています。
これから議論が進められ、例年ですと12月中旬頃に、税制改正大綱が公表されます。
主な要望事項は、以下の通りです。
今後の議論の行方に注目です。
【日税連】「やさしい税金教室」「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」について
日本税理士会連合会から、
平成30年度版の「やさしい税金教室」と「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」
が、公表されました。
この小冊子は、毎年改訂版公表されています。
「やさしい税金教室」は、Q&A形式で、税金について解説してあります。
「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」は、ライフステージごとに必要となる税金の知識を紹介してあります。
という切り口でまとめられています。
是非ご一読下さい。
【時事通信】20年からスマホ決済OK=はがきや宅配便料金-日本郵便
日本郵便では、2020年2月から、郵便窓口において、キャッシュレス決済を導入するそうです。
クレジットカード、電子マネー、アプリ(スマホ)決済が利用できるようになります。
利用できるのは、郵便窓口における切手・はがき、レターパック及び物販商品等の商品(印紙を除く。)
の販売並びに郵便料金及び荷物(ゆうパック、ゆうメール等)運賃の支払いです。
キャッシュレス決済が徐々に広がっていますね。
来年(2019年)10月1日から、消費税率が10%に引き上げられ、軽減税率制度が導入される予定です。
軽減税率の対象品は、飲食料品と新聞ですが、これらの財源として1兆円が必要で、
すでに0.4兆円は確保出来ているようで、残りの0.6兆円分を検討中のようです。
所得税やたばこ税の引き上げなどが、案として挙がっているようです。
今後、来年度税制改正大綱が12月公表予定ですが、議論が進められます。注目していきましょう。
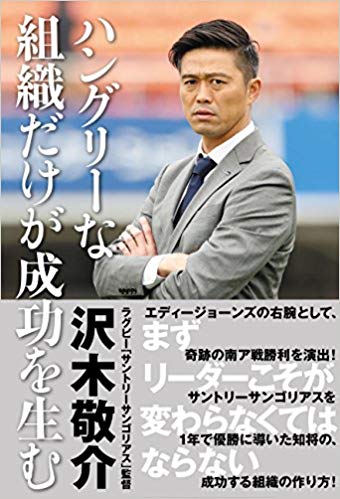
今年も国内のラグビーシーズンが到来しました。
ジャパンラグビートップリーグでは、3連覇を狙うサントリーを中心に激しい戦いが繰り広げられると思います。
さて、そのサントリーの監督である沢木敬介氏の著書「ハングリーな組織だけが成功を生む 」が、昨年12月に出版されています。
すでにお読みになった方もいらっしゃると思います。ビジネスでも大変参考になる内容です。
「コーチとは、もともと英語の「coach」つまり「四輪馬車」からきた言葉で、
コーチの役割は、選手たちをそれぞれが求める目標に到達させることにある。」
という冒頭の部分が特に印象的でした。
以下に第1章の目次を掲載します。これだけでも、上に立つ者の考え方が詰まっています。
是非ご一読下さい。
第1章 「ハングリーなチャレンジ」で1人ひとりの力を最大限に伸ばす
チームの「カルチャー」が薄れたことへの危機感
トレーニングは「全員一律」ではなく「個別」に
「競争」を生むためのキャプテン選び
「規律」を守ることで「自由」になるカルチャー
選手が自ら考えて「結果」を出す環境作り
選手を「居心地良く」させないプログラム
「やる気」を引き出すための「個別面談」
前年度王者を倒して芽生えた「自信」
「一戦必勝」が生んだ「全勝優勝」
採用の条件は「本物の負けず嫌い」
アドバイスには必ず「考える隙間」を残す
【時事通信】高額返礼品に対抗措置も=ふるさと納税、制度見直し検討-総務省
ふるさと納税では、高額返礼品が問題視され、昨年4月に、返礼品は寄付額の3割以下にするよう、総務省通知が発せられました。
その後、総務省通知に従い見直した自治体とそうでない自治体があることが、
調査結果により判明しました。(詳細はこちら ↓)
【総務省】「ふるさと納税に関する現況調査結果(平成29年度実績)」公表【2018年7月10日付ブログ】
今後、総務省通知に従わない自治体に対するふるさと納税については、
住民税控除((寄付額-2,000円)×10%)が認められなくなるかもしれません。
今後の動向に注目です。
【中小企業庁】先端設備等導入に伴う固定資産税ゼロの措置を講じた自治体を公表します
中小企業庁から、「先端設備等導入に伴う固定資産税ゼロの措置を講じた自治体」が、公表されました。
「生産性向上特別措置法」により、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業は、
自治体の判断により固定資産税の特例がゼロとなります。
なお、「先端設備等導入計画」は、認定支援機関の確認を受ける必要があります。
この制度においては、「先端設備等導入計画」の認定を受けた後に、設備投資をする必要がありますので、ご注意下さい。
【日経】「現金お断り」じわり増 AIレジ、カード限定ホテルも
キャッシュレス決済の動きが広がっているようです。
「現金お断り」という店が増えてきたり、大手銀行がサービスの開発に急いだり、
大手企業が普及のために採用をしたり、という状況です。
また、政府でも、補助金や税制優遇により普及を促す検討がされています。
こちらをご覧下さい↓
【日経】決済電子化で税優遇 政府検討「QR」など導入促す 【2018年8月23日付ブログ】