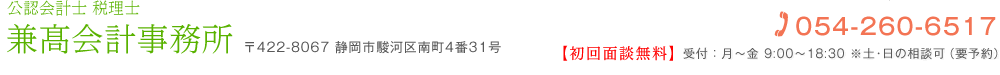【経済産業省】平成29年度予算「事業承継補助金」の概要を公表します
5月8日から「事業承継補助金」の募集が始まります。
事業承継に伴い、経営革新を行う場合、最大200万円
さらに、事業所の廃止や既存事業の廃止・集約を伴う場合、最大500万円
となっています。
応募する際には、経営革新等支援機関の「確認書」が必要となります。
経営革新等支援機関は、会計事務所、金融機関、商工会議所などが、認定を受けています。
事業承継を考えている方、事業承継に伴い経営革新等を検討している方は、是非この補助金の応募をご検討下さい。
詳細はリンク先をご覧下さい。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
事業承継対策、後継者育成のアドバイスやセミナー講師を承っております。
また、当事務所は、経営革新等支援機関です。
お気軽にご相談下さい。
お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。