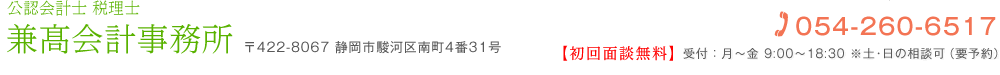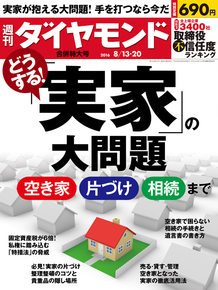皆さん、相続(税)対策は、万全でしょうか。
2015年1月1日以降、基礎控除額が引き下げられ、相続税を支払わなければならない方が増えました。
「我が家は、大した財産がないから・・・」と思っている皆さん、
ご自身が経営されている会社の株式の評価額が、驚くほど高くなっている場合があります。
特に、歴史が長く、たとえ最近業績が悪くても、業績が良い時代が長く続いて、内部留保が厚い場合は、株価が高いことが予想されます。
残された方は、多額の相続税支払義務が生じる一方で、会社株式を簡単に換金できずに、納税資金に困る・・・
ということがありえます。
残された方が困ることのないように、対策が必要です。
まずは株価を算定し、次に、今相続が発生したら、相続税がいくらになるか試算してみましょう。
なお、株価の算定、相続税額の試算は、複雑ですので、専門家にご相談下さい。