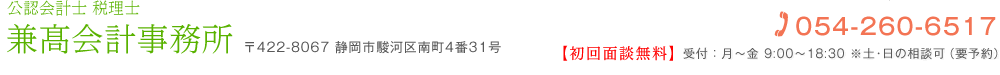【国税庁】「財産評価基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)
「財産評価基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)が、パブリックコメントにかけられています。
意見募集は3月30日までとなっています。
今回の改正は、取引相場の株式の評価と、森林の立木の評価です。
取引相場の株式の評価に関しては、以下の点が改正される予定です。
- 類似業種の株価について、2年間平均を追加
- 類似業種の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映
- 配当金額:利益金額:簿価純資産価額= 1:1:1に変更(現行1:3:1)
- 評価会社の規模区分の金額等の基準を見直し
今年1月以降の相続・贈与から適用予定です。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
また、ご意見のある方は、リンク先の提出先に、3月30日までにお送り下さい。